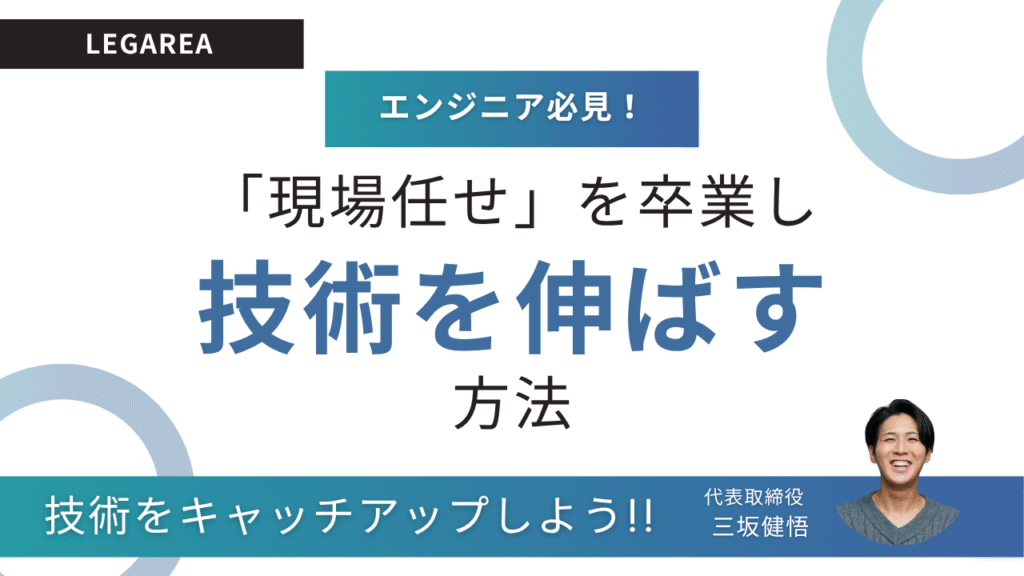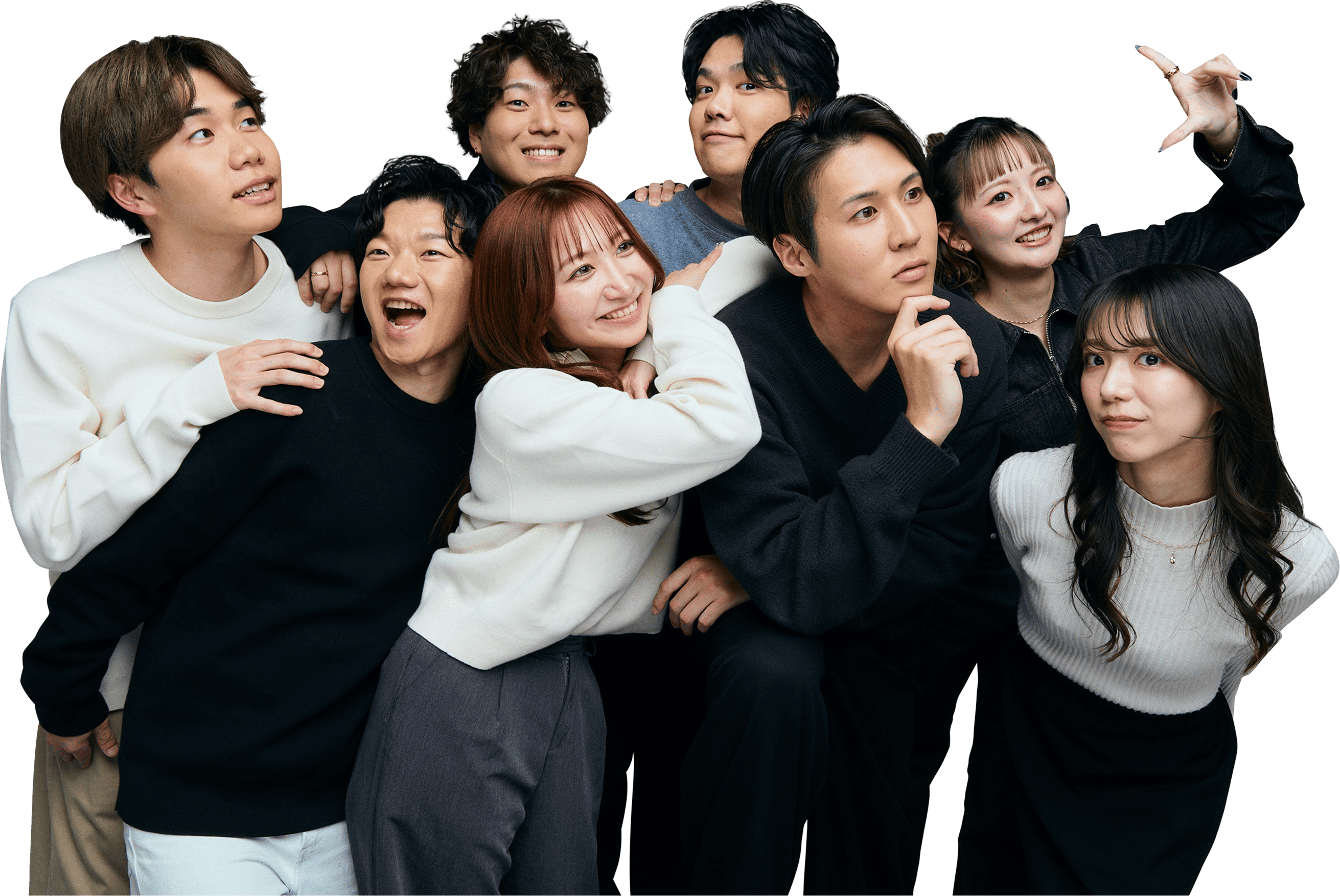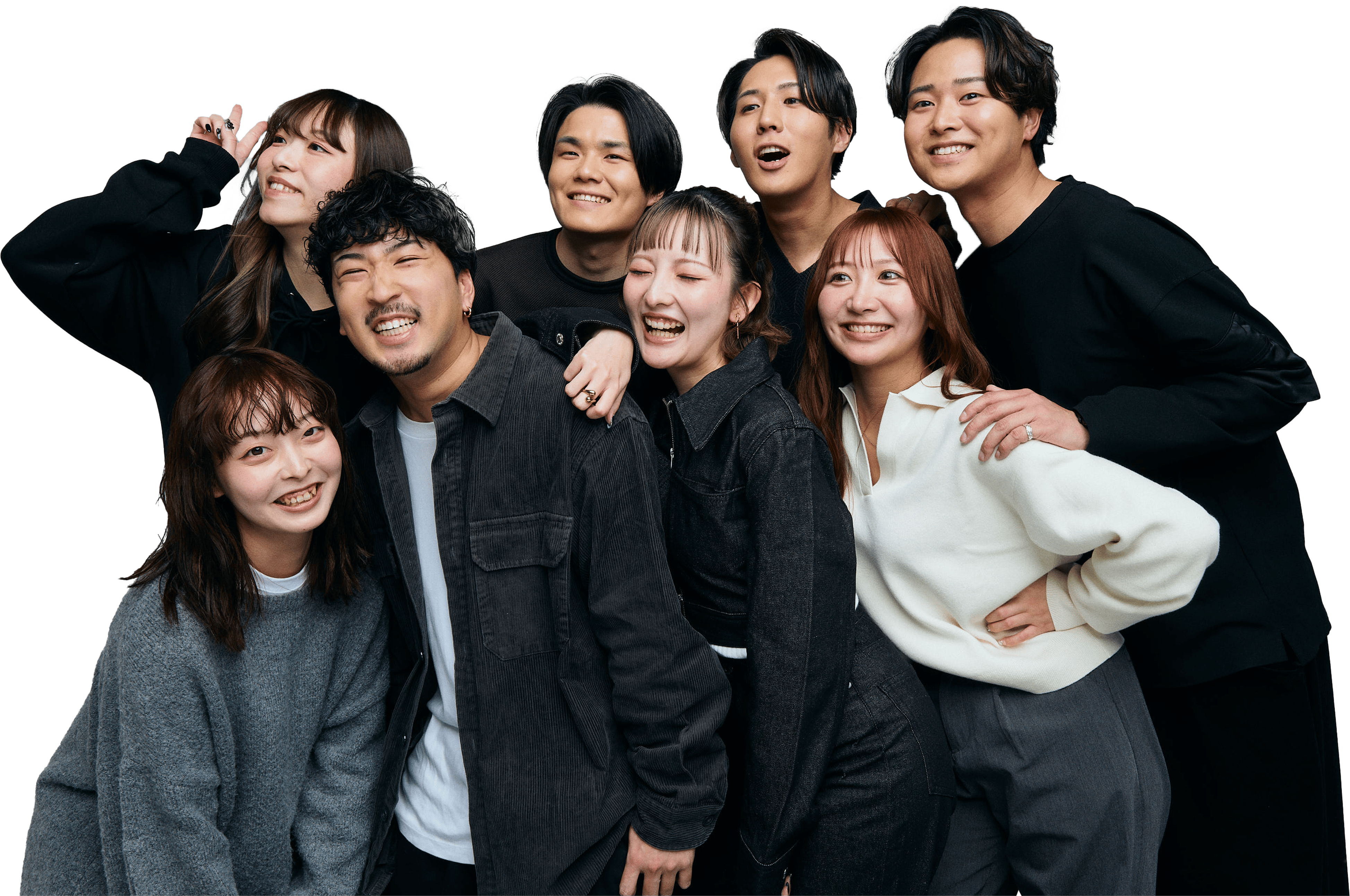はじめに:「この現場じゃ成長できない」と嘆く前に
この業界にいて、後輩や同僚から一番よく聞く言葉があります。
「今の現場、全然スキルアップにならなくて…」
「保守だけで毎日同じ作業なんですよ」
「テストばっかりで、開発やらせてもらえない」
その気持ちは痛いほどわかります。
SESという働き方は、配属された現場によって得られる経験値に大きなバラつきがある。
だから、スキルを現場任せにすると「伸びる人/停滞する人」の差がどんどん広がっていきます。
技術は、現場で学ぶものではなく、取りに行くもの、だぜ!!!
SESで生き残り、10年・20年と現場で価値を出し続けるには、
自分自身で“技術を取りにいく姿勢”と“続ける習慣”を持つことが不可欠。
今回は、「どうすればSESという制限のある環境でも、技術キャッチアップを続けられるのか?」を解説します。
なぜ“現場任せ”では成長できないのか?
❌「スキルがつく現場に入りたい」=“他力本願”の思考
たしかに、スキルの高い現場に入れば、成長スピードは上がるかもしれません。
でも、そういった案件は面談で求められるレベルも高い。
「現場で学ばせてください」は通用しません。
つまり、「スキルがないからスキルが欲しい」という循環では、いつまで経っても現場に入れない。
✅ 現実:キャッチアップは“案件に入る前”に済ませておくもの
たとえばAWSやLaravelのような技術でも、
最低限の基礎を自習しておかないと、現場に入れても“活かせない”どころか“足を引っ張る”。
「現場で学ぶ」ではなく、「現場に入るために学ぶ」
この順番を入れ替えるだけで、SESエンジニアのキャリアは大きく変わります。
SESで技術を伸ばし続ける人の共通点
技術が伸び続ける人にはいくつかの共通点があります。
✅1. 「自分の伸ばしたい領域」が言語化できている
漠然と「スキルアップしたい」ではなく、
- 「インフラ自動化に強くなりたい」
- 「Laravelを軸にWebアプリ開発を極めたい」
- 「クラウド×セキュリティを掛け合わせたい」
のように、“伸ばしたい方向”が明確な人は、キャッチアップがブレない。
✅2. 「現場で得られないものは、業後に補う」姿勢がある
たとえ運用保守の案件でも、
- 勉強会に出る
- ハンズオンでAWSを触る
- 個人開発で触ってみる
…といったように、“学習の主導権を自分で握っている”。
✅3. 「技術を誰かに説明する」アウトプット癖がある
- Qiitaで記事を書く
- 社内でナレッジを共有する
- ChatGPTに教えるつもりで整理する
学んだことを言語化・再構築することで、記憶と応用力が飛躍的に上がります。
技術キャッチアップを習慣化する5つの具体ステップ
ステップ①:「今後伸ばしたいスキル領域」を3つ書き出す
例:
- Laravel
- Git運用
- CI/CD(Github Actions)
書き出すことで、自分の学習軸が定まります。
ステップ②:「週1回だけ、技術投資の日」を決める
例:毎週水曜の夜は技術の日(1時間だけ)
毎日やるより、週1を継続した方が効果的。
平日ルーティンの一部にすることが鍵です。
ステップ③:インプットとアウトプットの比率を「3:7」にする
- インプット(本、記事、動画)
- アウトプット(手を動かす、ブログに書く、人に話す)
情報を“自分の言葉にする”アウトプットの方が、圧倒的に記憶に残ります。
ステップ④:「個人用ポートフォリオ環境」をつくる
例:
- Githubで自分の学習用リポジトリを管理
- Dockerでローカルに学習環境を再現
- Notionに技術ログを残す
小さくても“自分の技術基地”を持つことで、学習が資産になります。
ステップ⑤:「社外の刺激を月1回取り入れる」
- 勉強会参加(connpassなど)
- オンラインイベント視聴
- 知人エンジニアと情報交換
SESの課題は“閉じた空間”に閉じこもりやすいこと。
月1回、外からの刺激を入れるだけでモチベーションが復活します。
おすすめ学習リソース
📚知識のインプット
- Zenn / Qiita:日本語記事の宝庫
- ドットインストール:短時間で手軽に動画学習
💻手を動かす
- Progate:基礎をなぞるには最適
- CodeSandbox / Stackblitz:環境構築不要で試せる
- TechTrain / paiza:ゲーム感覚で学べる
🧠アウトプット先
- Qiita/Zenn(投稿)
- Github(コード化)
- X(短文メモ)
- Notion(学習ログ)
「やらなきゃ」ではなく「やったほうが得」な状態へ
学習が続かない理由の多くは、「やらなきゃ…」という義務感。
でも、続けている人の共通点はこうです:
「自分が得するからやってる」
「結果的に面談で話すネタが増えた」
「単価が上がった。自由が増えた」
つまり、技術キャッチアップは未来の自分の営業資料です。
やったことは全部「武器」になる。
面談、転職、社内評価、すべてに効いてくる。
SESという働き方だからこそ、学びを“自分で獲る”
SESは、決して“学べない働き方”ではありません。
むしろ、案件を選べるからこそ学び方を選べる働き方です。
でも、そのためには準備が必要。
そしてその準備こそが、キャッチアップであり、習慣です。
技術は裏切りません。
でも、現場はあなたの学習まで面倒を見てはくれない。
だからこそ、自分の意思で技術を獲りにいく。
それが、SESエンジニアの生存戦略だと私は思います。