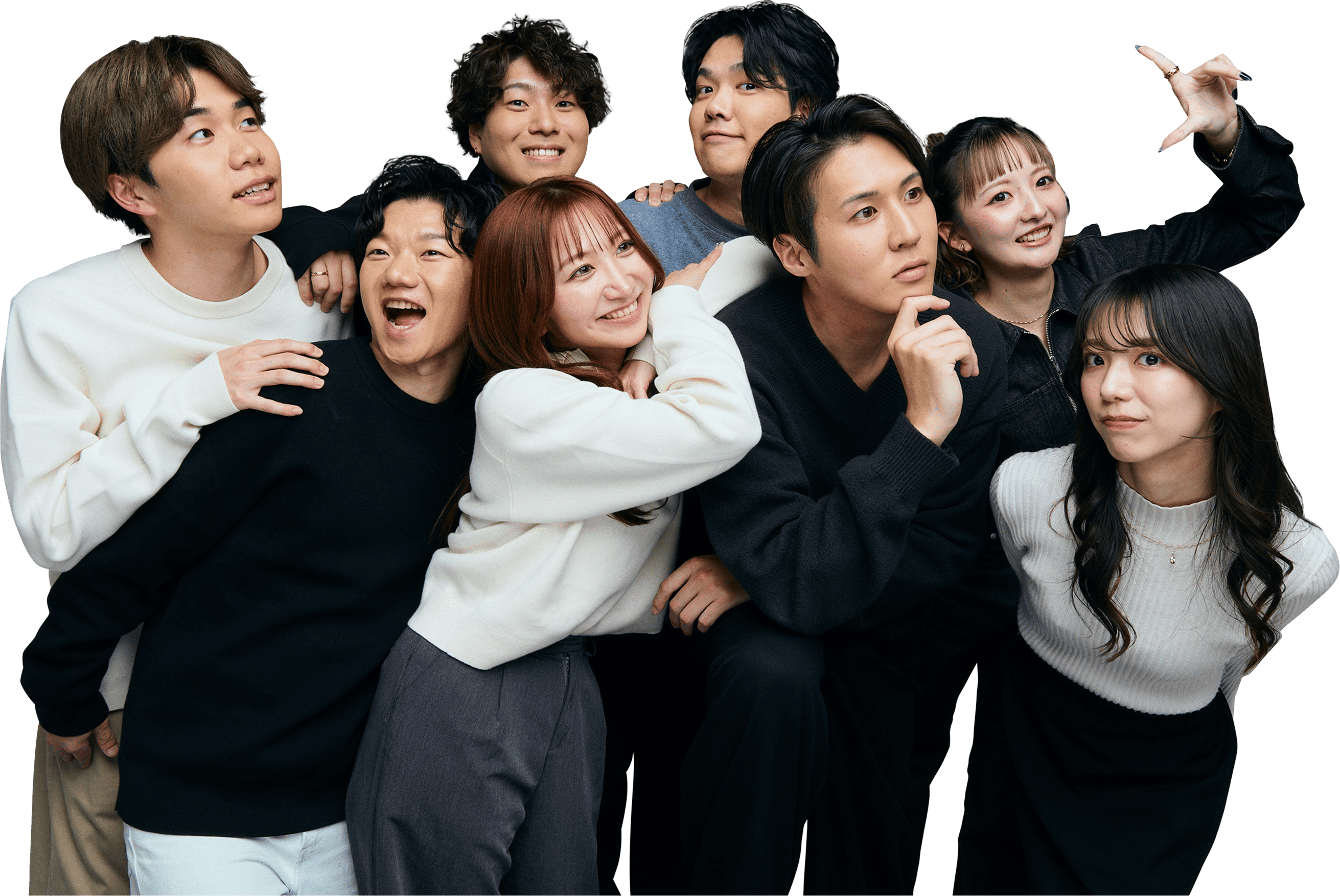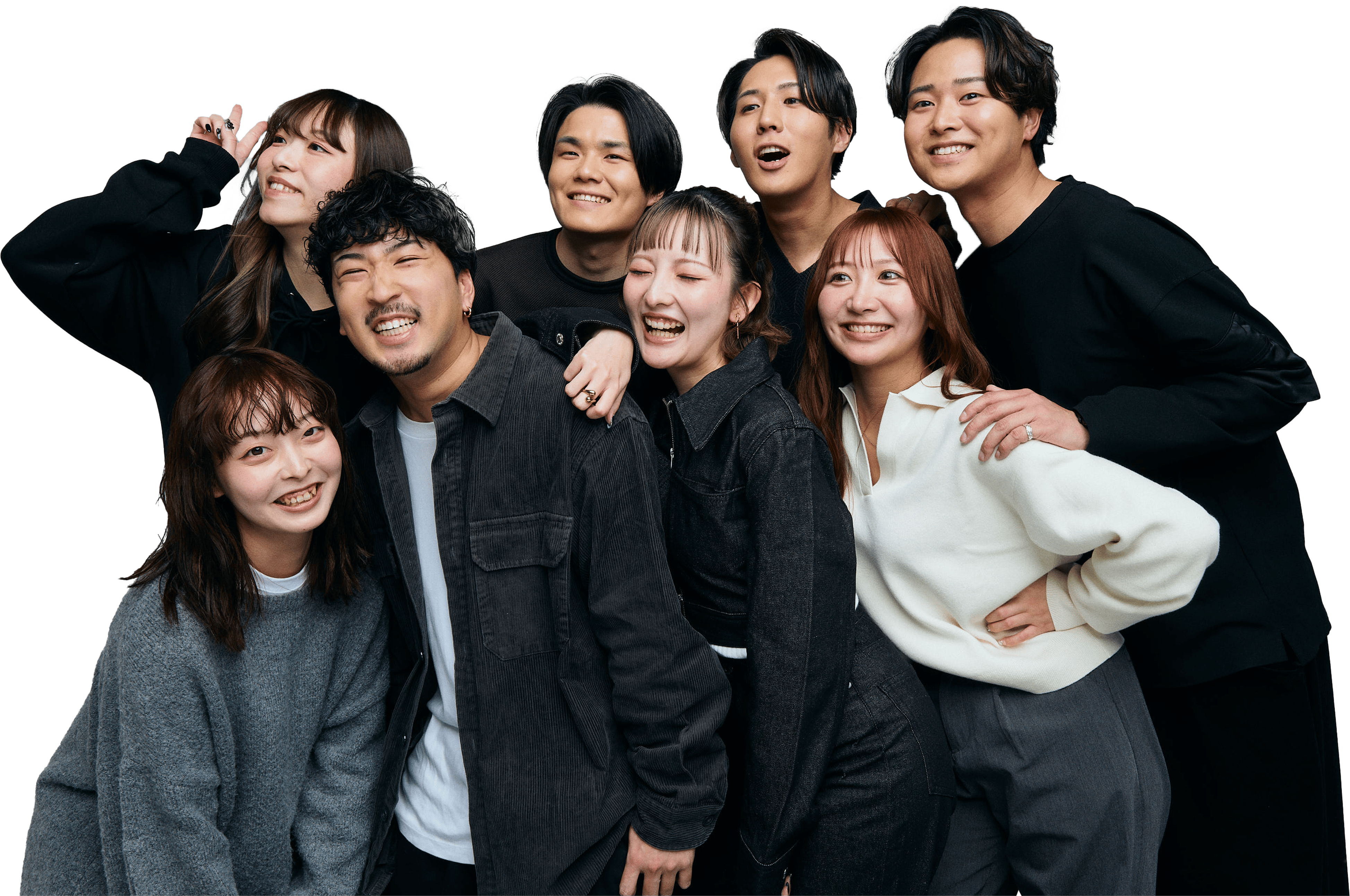こんにちは、LEGAREA代表の三坂です。
最近、Netflixの怪獣8号にハマっています。鳴海隊長のファンです。
その中で、どうしても、気になります。どうやってNetflixは作っているんだ?と
ただ実際にその裏側を覗いてみると、やっぱり簡単な話じゃないんですよね
ただの動画配信ではなく、世界中で同時に何億人もが視聴する、圧倒的なUXを保ったまま動き続けるインフラ。そこにはシンプルな構成の裏に、とんでもないロジックと執念が詰まっているはずだと考え、調べました。
今回は、そんなNetflixを構成するインフラ要素をロジカルに分解してみたいと思います。
なぜNetflixを作るのは難しいのか
1. 水道インフラを自分で世界中に引いている
Netflixの裏側を一言で言えば、動画専用の水道管を、地球規模で自前整備している企業です。
例えば、YouTubeで1分の動画を見るだけでも、数MB〜数百MBの通信量が発生します。
映画となると、1作品あたり数GB〜10GBのデータが流れる。これを、世界中で数百万人が同時に再生している。
普通のWebアプリであれば、画像やテキスト中心の軽量データ。
でも、Netflixはリアルタイムで何億リクエスト分の超重量データを送り続ける必要があります。
しかも、再生ボタンを押したその瞬間に、です。
だから、AmazonのようにAWSを借りて…ではなく、自社で世界中にCDN(動画の配信拠点)を設置しています。
このCDN(Content Delivery Network)によって、最短ルートで動画が届くようになるんです。
2. 家の近くにスーパーを建てている理由
もっとわかりやすく説明しましょう。
Netflixのやっていることは、家から遠い大都市にあるスーパーまで買いに行かずに済むように、各町に小さなスーパー(CDN)のようなものを自分たちで作る。そこに、あらかじめ冷凍食材(エンコード済みの動画)を詰めておく。
すると、映画を観たいと思った瞬間に、最寄りスーパーから最短時間で配達できる。
これがCDN分散という考え方です。Amazon CloudFrontやAkamaized.netを使う企業が多い中で、NetflixはOpen Connectという自社CDNを構築・運用している点が最大の特徴です。
3. 「一人ひとりに合わせてお弁当を詰める」=動画のエンコーディング
動画って、スマホでもテレビでも、同じように観られますよね。
でも実際は、1つの動画を、複数のサイズ・解像度・圧縮率で用意しているんです。
- 通信が遅いユーザー用に:解像度480p
- 高画質を求めるユーザー用に:4K HDR
- 小さい画面向けに:圧縮&軽量化
- 通信が途切れても再生できるよう:チャンク分割
これらを全部、再生環境に応じて自動で出し分けする。これが「アダプティブ・ストリーミング」という技術です。
さらに、世界各地のスーパー(CDN)に、この複数のお弁当をあらかじめ詰めておく。
そうしないと、あなたの家に配達されるまでに何秒も遅れてしまうんです。
4. 「再生ボタンを押した瞬間に動かす」レイテンシ最適化
動画配信の最難関はここです。
- YouTubeで3秒止まる
- Netflixでカクカク再生される
たったこれだけで、ユーザーは離脱します。
Netflixでは、この最初の3秒に命をかけている企業です。
だから、「再生ボタンが押された瞬間に、最初の1〜2秒分だけ超高速で配信」できるような最適化がなされています。
しかもそれを、全世界、全時間帯、全デバイスで実現している。最初の一口目で勝負する設計が、NetflixのUXを支えている理由です。
5. 「何を見せるか」がUXの9割を決める
Netflixのトップ画面、人によって全然おすすめが違いますよね。
- 過去に観た映画のジャンル
- どのサムネに反応したか
- 平日と休日の視聴傾向
- 同じ動画でも表示順が違う
このパーソナライズされた世界を作っているのが、メタデータ × レコメンドAIです。
ここで面白いのが、「サムネイル自体もその人ごとに変わっている」という点。
つまり、映画そのものじゃなく、入口の見せ方でCTRを変えている。
TikTok、Instagram、YouTubeも同様のアルゴリズムですが、NetflixのそれはUXの一部としてチューニングされている点で非常に精巧です。
Netflixは「技術」ではなく「執念」でできている
ここまで見てきてわかる通り、Netflixを構成する技術はどれも業界最先端ですが、個別の技術そのものが革新的なわけではありません。
- CDNは他社にもある
- エンコーディングはAWSでもできる
- レコメンドAIも一般的になった
でも、Netflixはそれらを限界まで突き詰めて仕組みに落とし込んだ。
しかも、「視聴者の体感速度」や「離脱率」を最重要KPIに置き、
毎月数千のA/Bテストを繰り返し、レイテンシや帯域やサムネイル最適化を秒単位で改善し続けている。
いわばこれは、インフラではなく哲学の話で、少しスピった感じに聞こえたらすみません。でも本当にすごいことなんです。
Netflixから学べること
- 目に見えないUXにこそコストと技術をかける
- チーム全員が最初の3秒に命をかける意識を持つ
- CDNのように先回りして価値を届ける設計思想
- 再生ボタンを押す前に、感情を設計するレコメンド思考
これは、Webアプリでも、社内業務改善でも、営業資料でも、全部同じです。
Netflixは映画を届ける会社ではありません。
体験を止めない会社というのが正しいかもしれません。
おわりに
Netflixのインフラは、単に強い技術で作られているわけではありません。どんな状況でも視聴体験を止めないという、UXへの徹底したこだわりと、ビジネス継続性への設計思想が、随所に滲んでいます。こういう構成を見るたびに、ただシステムを組むのではなく、どんな価値を届けるかを起点に設計することの大切さを再認識させられます。少しでもこの記事が、インフラ設計に興味のある方や、動画サービスを学びたいエンジニアの方のヒントになっていたら嬉しいです。