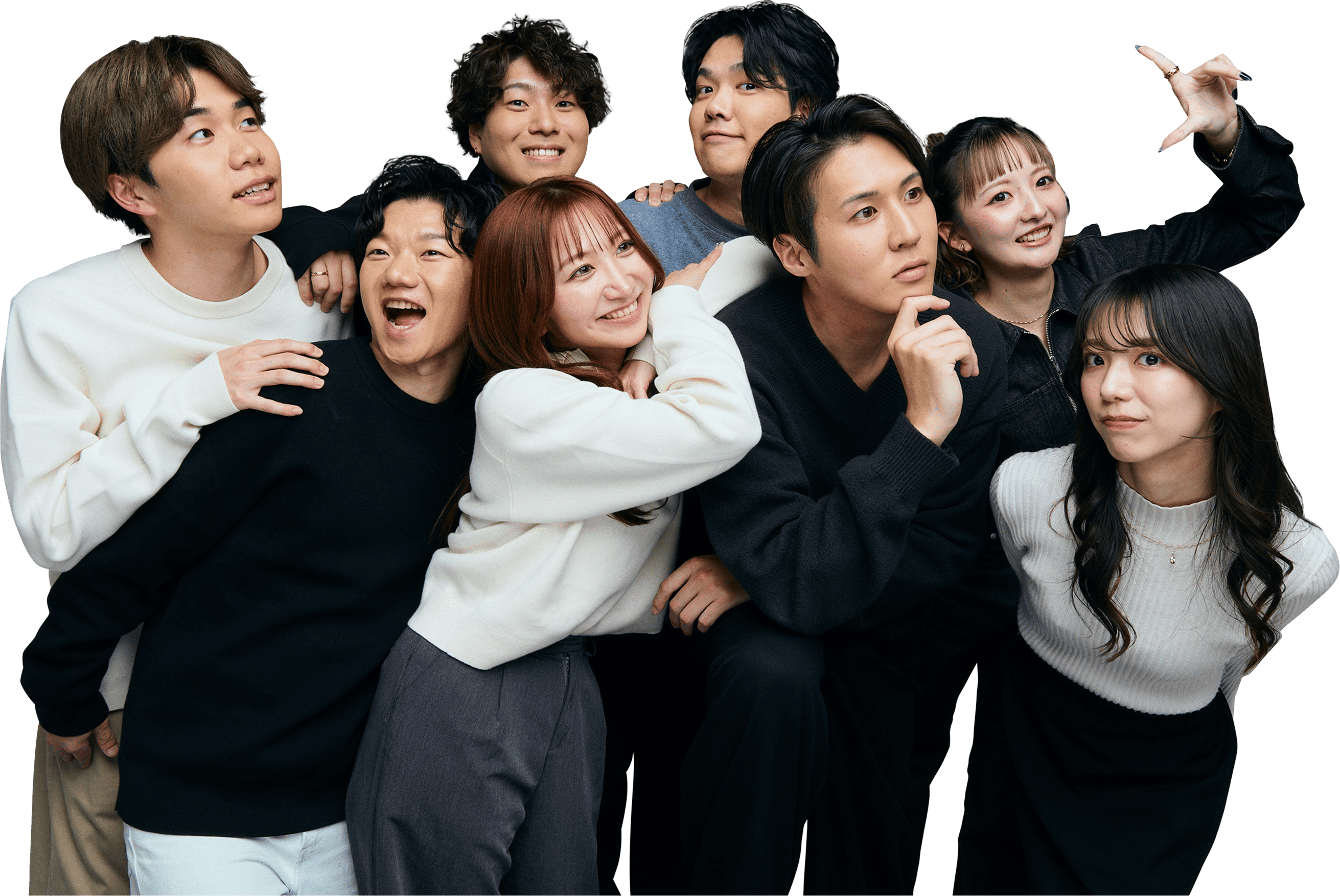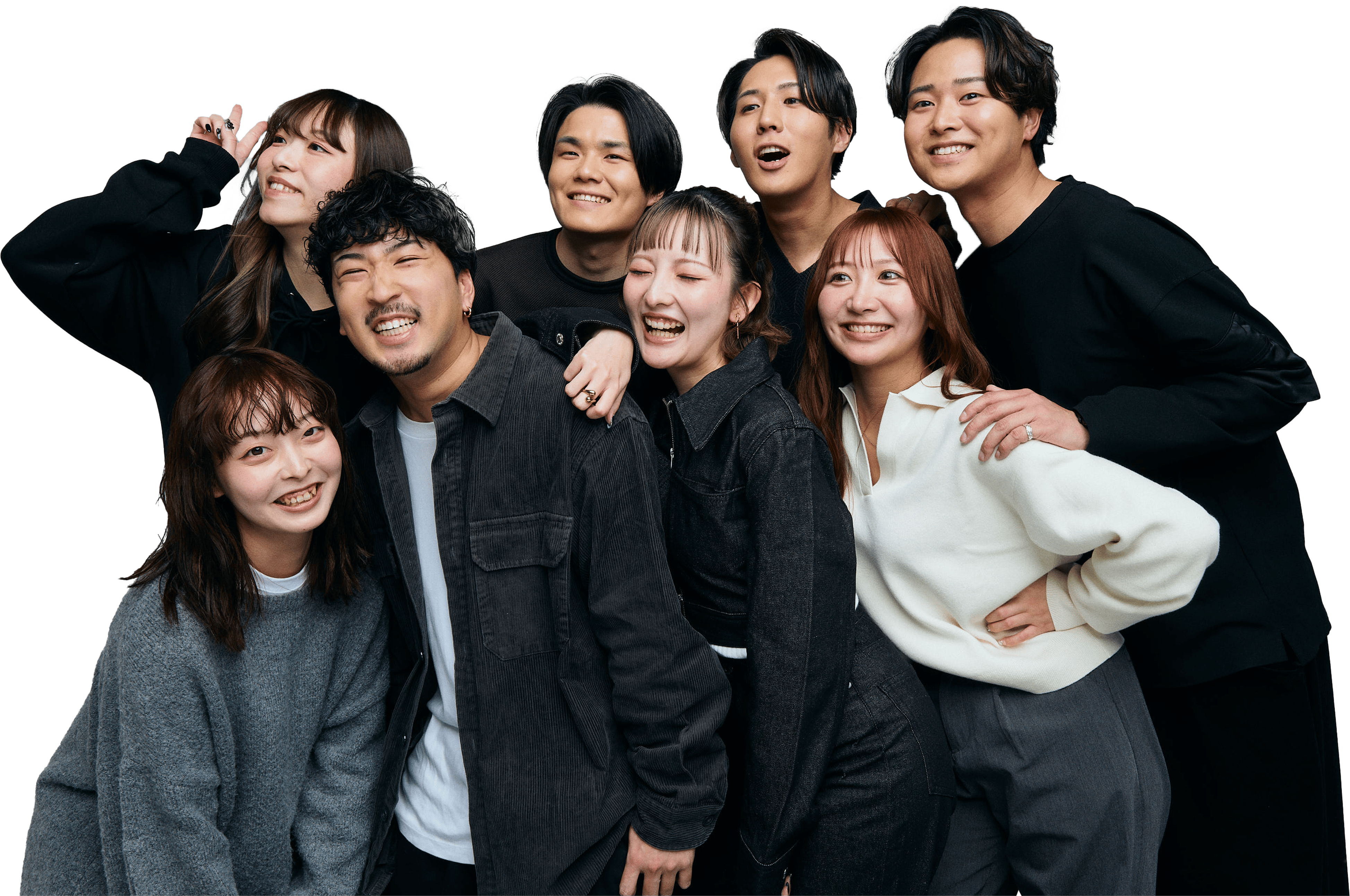こんにちは、代表の三坂です。
SESという働き方を10年以上見続けてきて、心から思うことがあります。
技術がある人が評価されるとは限らない。
むしろ、空気を整えられる人のほうが、現場で生き残っていく感覚があるんですよね。
今日はそんな、空気を動かせる人について、少し深掘ってみたいと思います。
なぜ空気が、技術より大事になるのか
SESの現場って、言ってしまえば他人の家に住むような仕事だと思っています。
文化も空気もルールも、その会社独自のものがあって、
そこに外部の人間として入っていく。
そんな環境の中で、うまくやっていくには、
コードの正しさよりも、人としての扱いやすさのほうが求められる場面が多いんじゃないでしょうか。
実際に僕が見てきた中でも、
・特別なスキルがあるわけじゃないのに、なぜか継続率が高い人
・特に目立ってないのに、クライアントから信頼されてる人
・毎回別の現場でも歓迎される人
こういう人たちって、だいたい空気を読んで動ける人だった気がします。
空気が悪くなる瞬間って、どこにある?
SESの現場にいると、明文化されてない空気のルールってたくさんありますよね。
たとえばこんなシーン、経験ないでしょうか?
・朝会で誰かの返事が明らかにトーン低くて、その後みんな急に静かになる
・チャットで雑談がぱたっと止まり、仕事の話だけになる
・週明け、特定の人の姿がないだけで空気がピリつく
・議事録の最後、誰もフォローせず“じゃ、おつかれさまでした…の沈黙
・タスクが詰まりはじめると、全員が急にSlackの既読をつけなくなる
こういう言葉にならない違和感って、SESにいるとよく起きます。
でも実は、ここに最初に気づいて空気を調整できる人こそ、
現場で重宝される人なんだと思うんです。
空気を動かせる人が持っている、見えない3つの力
では、空気を動かせる人って、実際に何をしているんでしょうか?
スキルでもなく、発言数でもなく、僕なりに分析してみると、共通しているのはこの3つでした。
1. タイミングの感覚が異常に鋭い
空気を読める人って、何を言うかよりもいつ言うかにセンスがあるんですよね。
たとえば朝会で、
・誰かが詰まっていたとき、ほんの少しだけ質問を投げて助け船を出す
・リーダーの指示が曖昧だったとき、誰よりも先に具体化する質問を投げる
・締めが弱かった会議の後に、“皆さんお疲れさまでした”とチャットでひと言添える
これだけで、場の温度って変わっていきますからね
2. 自分の感情に自覚的である
空気を乱す原因って、実は自分の感情のままに行動する人にあると思っています。
でも、空気を整えられる人は、
自分の機嫌や疲れを相手にぶつけないんです。
むしろ、
・今日は少し落ち込んでるので静かです
・反応鈍いかもですが、ちゃんと見てます
こんなふうに、先に伝えることで、相手に気を遣わせない空気をつくってるんですよね。
これができる人は、安心して仕事を任せられる気がします。
3. その場の不安に気づく力がある
どんな現場でも、誰も言わないけど全員が思っていることってありますよね。
・進捗が遅れてるのに、誰も突っ込まない
・お客様のトーンが厳しくなってるのに、空気が止まってる
・議論がどこかズレているのに、誰も止められない
ここに気づいて、ほんのひと言で整理できる人は、
実はPMでもPLでもないのに、チームの進行役になってたりします。
空気を動かすために、今日からできること
急に空気を変える人になれって言われても、難しいですよね。
でも、今日からできることはあると思っていて、
それは観察することです。
たとえば:
・この人が話すと空気が明るくなるな、と思ったらその話し方を真似てみる
・逆に、空気が止まった瞬間のきっかけを冷静に見ておく
・会議後にチャットを送る人が誰なのかに注目してみる
こういう観察を日々続けていると、
あ、今ちょっと声をかけた方がいいなという感覚が育ってきます。
空気を読むって才能ではなく、日々の小さな観察の積み重ねなのかもしれません。
最後に
SESという仕事って、スキルだけで評価されるものではないと思っています。
むしろ、感じがいい人一緒にいて安心する人”のほうが、
案件も長く続くし、クライアントからの評価も高くなる。
僕自身、技術に自信がなかった頃、
その場にいるだけでいい空気をつくるという部分を武器にしていた時期がありました。
だから今、もし自分に強みがないと感じていたら、
まずは“空気を整える”という選択肢を持ってみてほしいです。
この文章が、現場での自分の立ち位置を見直すきっかけになったら嬉しいです。
ではまた次回!