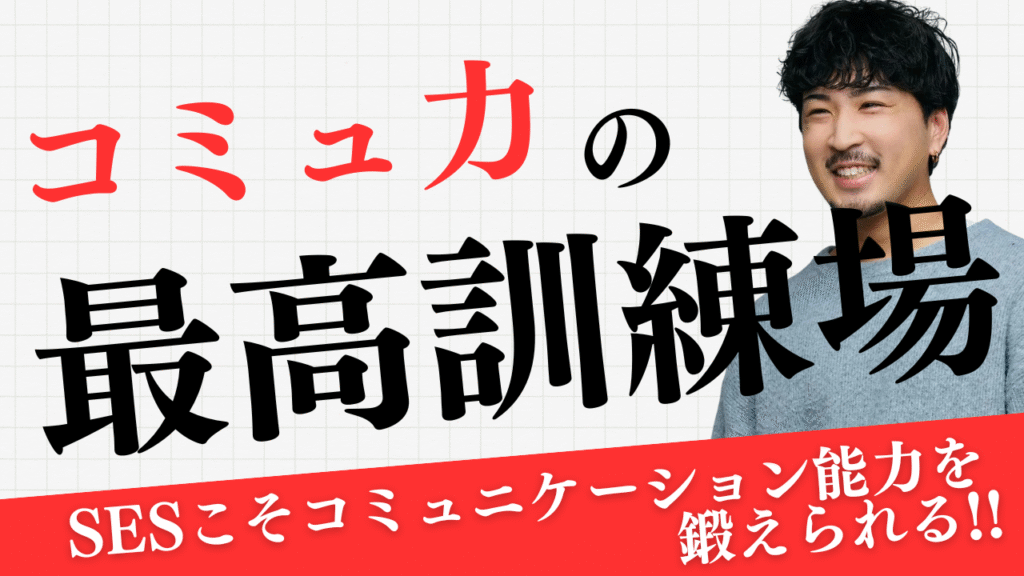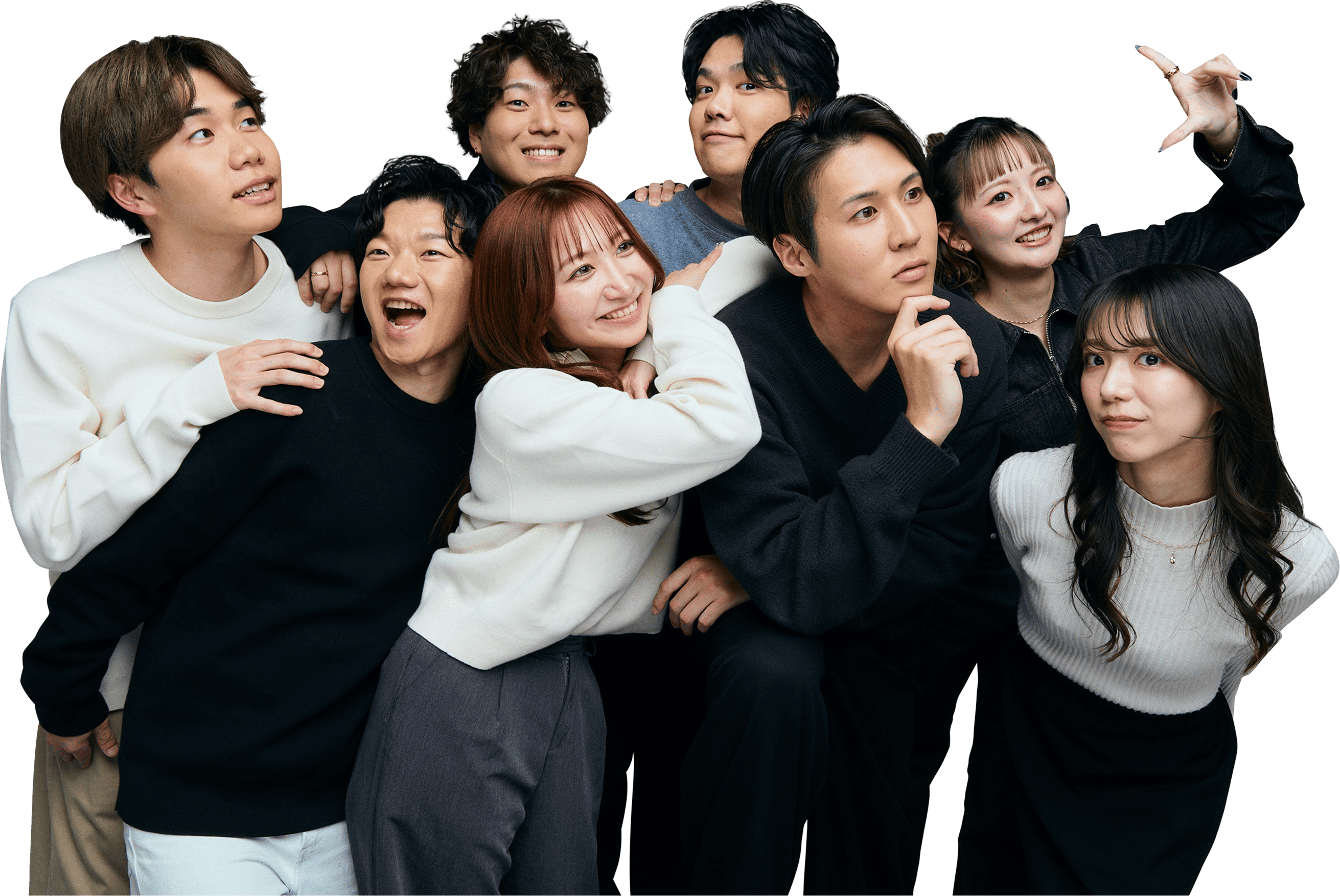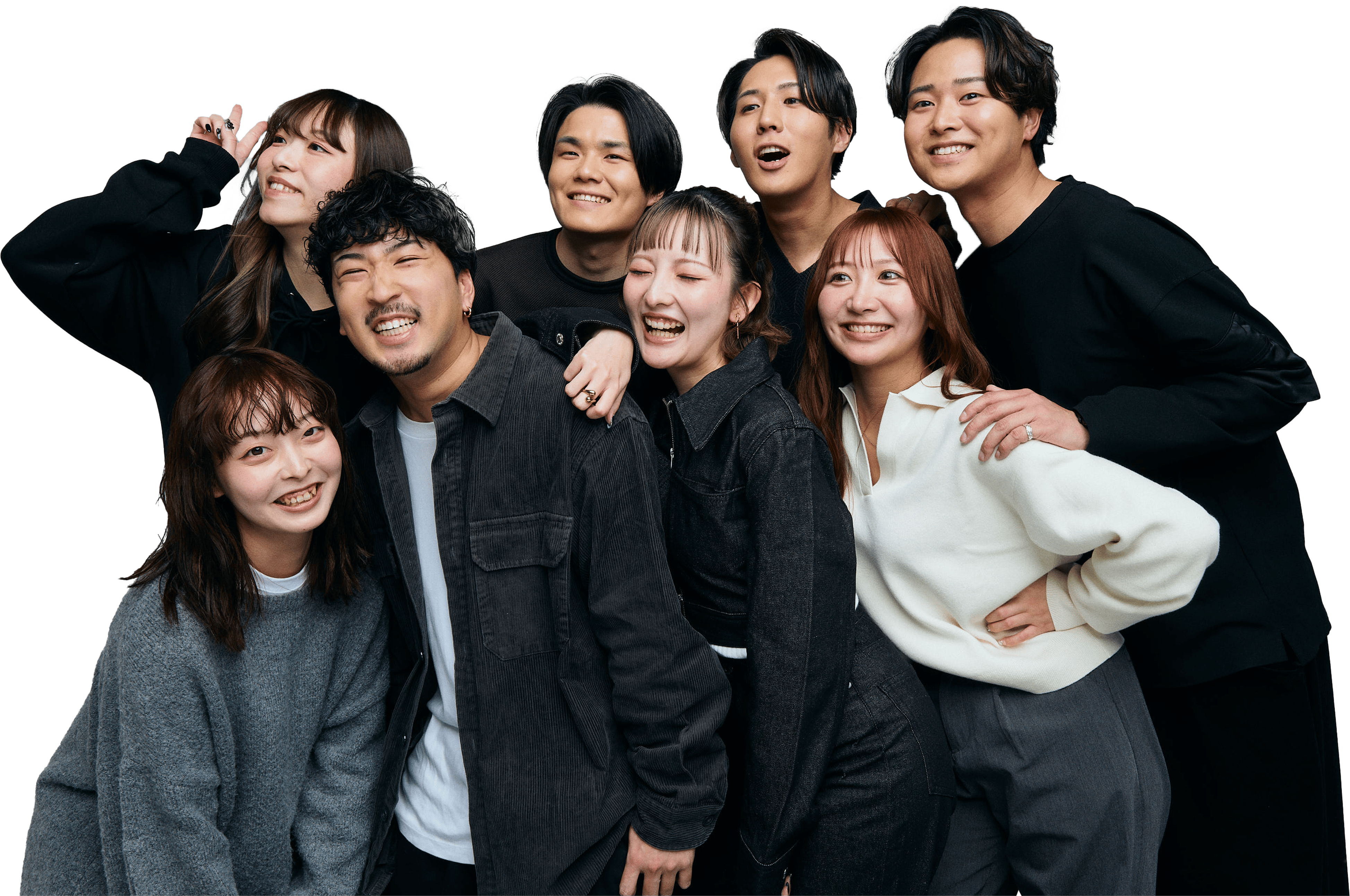暑い日が続きますね、代表三坂です。最近は広報活動に力を入れており苦手なSNSとにらめっこをしています。つらいです。SNSはもはやインフラなんですね。がんばっていきます。
さて、今日はほとんどの人の課題であると思われる、コミュニケーション能力について語っていきたいと思います。
【はじめに】エンジニアに「コミュ力」なんて必要なのか?
SESで働く中で、こんな言葉を聞いたことはないですか?
「技術職にそこまでコミュ力いらないでしょ」
「自分、陰キャで人見知りなんで会話無理っす」
「コードさえ書ければ評価されるって信じてたのに」
一度はあると思います。ですが、SESこそ、コミュ力の最高訓練場だと僕は思っています。
なぜなら、技術よりも関係構築で評価される世界だから。
今回は「SESという職種が、いかにコミュニケーション能力を鍛える修羅場であるか」を徹底的に解説します。
第1章:「技術職だからコミュ力いらない」は幻想
✅あなたが評価される基準は技術ではない
SESの現場での評価は、こんなロジックで下されます。
✅報告・連絡・相談が分かりやすいか
✅空気を読んで、タイミングよく動けるか
✅顧客の要望を“翻訳”して動けるか
✅トラブル時に人を巻き込めるか
つまり、コードスキル以前に、
人との摩擦を起こさない+気持ちよく仕事を進めるスキルが求められるのです。
✅SES現場は「技術」と「人間関係」のハイブリッド
SESは、いわば社外チームの一員。
そのため、以下のような非エンジニア的業務が多発します。
- 会議での要点まとめ
- 進捗の可視化と報告
- 顧客の曖昧な要望の読解
- チームの空気調整
技術職でありながら、PM的・営業的コミュ力が要求される。
つまり、技術とコミュ力のハイブリッド職こそがSESだと感じています。
第2章:SESがコミュ力養成ギプスな5つの理由
✅1. 「初対面×即日現場」の修羅場
SESでは、案件参画初日から知らないチームに放り込まれます。
- 業務フローがわからない
- チャット文化もわからない
- 誰に聞けばいいかもわからない
そんな中、嫌われずに距離を縮める能力が必要。
これを毎回繰り返すうちに、初対面耐性が圧倒的に強化されますよね。
✅2. 「報連相」の質=評価
SESでは、あなたの存在感は成果ではなく報連相で判断されます。
- 「この人、話が簡潔で助かるな」
- 「説明が的確で、状況が掴みやすい」
- 「困ってる時にちゃんと声を上げられる」
これだけで、「優秀な人」という評価がつく。
つまり報告スタイルが評価に直結する構造なんです。
✅3. お客様と同僚の境界線を読む訓練
SESは取引先という立場上、上下関係が複雑です。
- 現場社員が顧客でもあり、時にチームメンバーでもある
- 言いすぎれば失礼、黙れば役立たず
- 相談も、角度と順序を間違えると信頼を失う
→ このバランス感覚を掴む経験こそが、社会人力の核心となるところです
✅4. 「共感」と「技術翻訳」が求められる
現場のPM・上司は、技術に詳しくないことも多い。
だからこそ、
- 技術的課題を日本語で伝える力
- 顧客の「○○がうまくいかない」を技術に翻訳する力
- 「怒ってる理由は本質じゃない」ことを理解する力
こうした、聞く力と訳す力が異常に鍛えられますね
✅5. 人に信頼される技術者が一番重宝される構造
SES現場で一番求められる人材像、それは:
「あの人がいると助かるよね」って言われる人
そのためには:
- 技術的にそこそこ+人間的に気持ちがいい
- 自分で気づける人
- ミスしても素直に謝れる人
この人として好かれる力が、そのまま案件継続・単価UP・営業評価に直結します。
第3章:「SESで育つコミュ力」は一生モノ
✅プレゼン力が自然に身につく
進捗報告・相談・課題共有を日常的にやることで、
「相手の理解度に合わせて説明するスキル」が飛躍的に上がる。
→ 他業種に転職しても役立つ話の地頭が養われるでしょう
✅黙っていても伝わらないが骨身に染みる
SESでは、黙っていればできない人扱いされる。
だからこそ、
- 状況を伝える
- 先に断る
- 自分の認識を整理しておく
という先手のコミュ力が鍛えられます
✅「自分を説明できる力」が育つ
SESは常に面談+現場の繰り返し。
つまり、自分という人間を他人に説明し続ける仕事でもある。
- スキルシートの補足
- 面談時の説明力
- 営業へのフィードバック
- 自己紹介のチューニング
これらを何度も行うことで、言語化筋のようなものが鍛えられ、転職や副業でも大きな武器になることは間違いありません。
【まとめ】SESは、技術職のふりをしたコミュ力職である気がしています
SESで活躍する人の共通点は、
「そこそこ技術+圧倒的に感じがいい」人。
逆に言えば、「技術だけ」の人は絶対に評価されない。
SESという環境は、理不尽で面倒な人間関係の集合体かもしれない。
でも、それを「鍛錬の場」として活かせる人こそ、
技術もキャリアも人間力も、誰よりも伸ばすことができるのだと僕は考えています