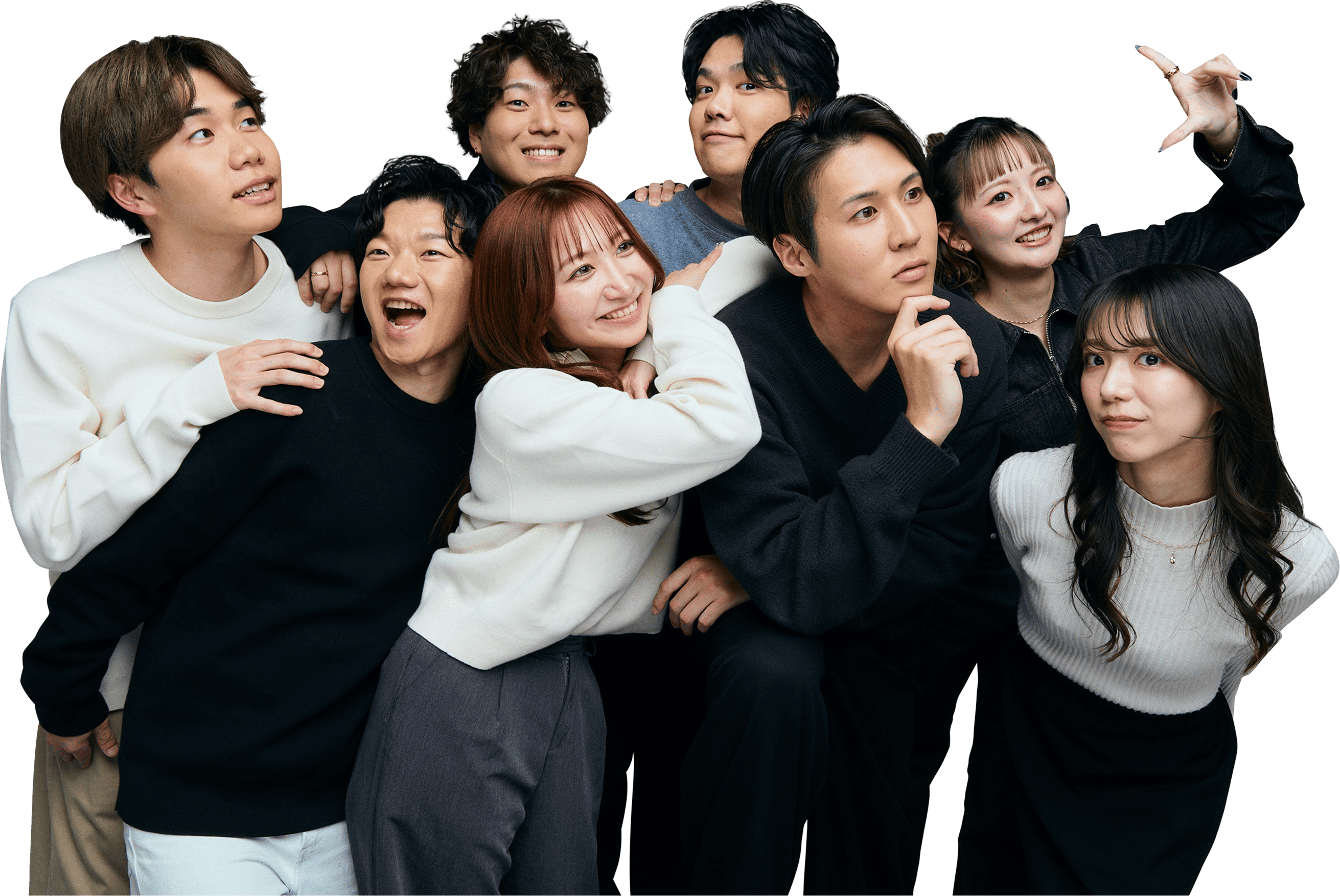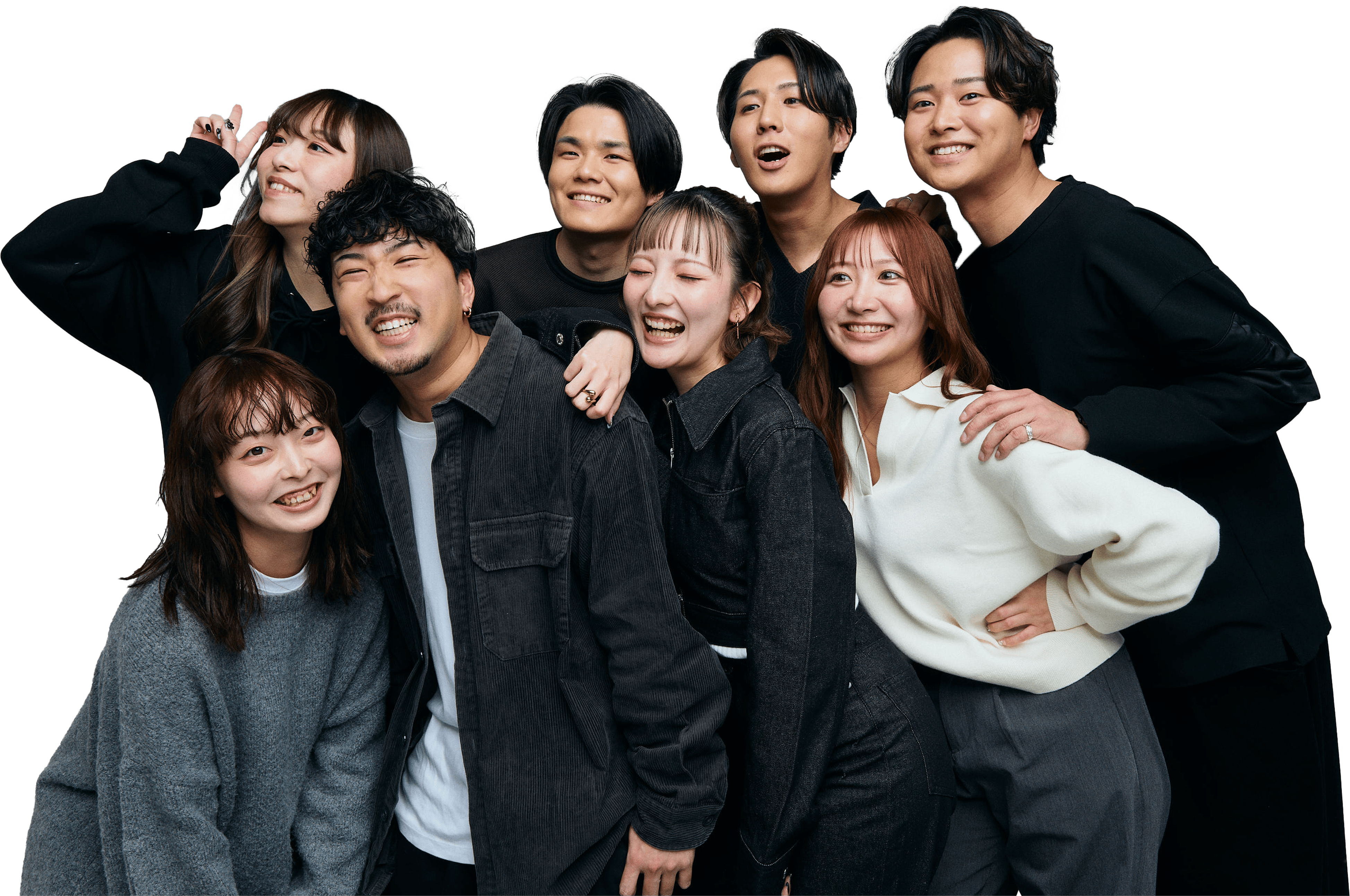こんにちは、LEGAREA代表の三坂です。
本日はAI時代に求められるエンジニアの軸のつくり方についてお話ししていきます。
最近、社内のキャリア面談でこんな質問をよく受けます。
自分はジェネラリストを目指すべきなんでしょうか
それとも、どこか一つに特化したスペシャリストになるべきなんでしょうか
この問い、実は僕自身もずっと考え続けてきたテーマでもあります。
なぜなら、SES業界で働くエンジニアは、複数の現場を経験していくことが前提であり、その中でどうキャリアを組み立てるかは、自分で判断していかないといけないからです。
そして今、その選択にAIという新しい軸が加わったことで、ますます迷いが深くなっていると感じています。
ジェネラリストという選択肢
ジェネラリストとは、広い分野にまたがって知識やスキルを持つ人です。
たとえば、Reactも書けるし、SQLも扱えるし、AWSの基本構成も理解している。あるいは、マネジメントや営業との折衝もできる。そういう人を指します。
メリットは、柔軟にどんな現場にも対応できること。
実際、SESのように現場単位で配属が変わる業態では、ジェネラリスト的な動きができる人は重宝されます。
ただし、気をつけたい落とし穴もあります。
それは、自分の軸がどこにあるのか分からなくなること。
どこでも活躍できるけど、どこにも強みがない。
そういう状態になってしまうと、年収交渉やキャリアアップの場面で不利になるケースもあります。
スペシャリストという選択肢
一方で、スペシャリストとは、特定の技術や領域に深く精通した人を指します。
たとえば、Flutterに特化してアプリのUI/UX設計ができる人
あるいは、SREとしてインフラの可用性や監視構成を設計・実装できる人
こういった人は、技術的な信用が高く、引き合いが来やすい特徴があります。
しかし、スペシャリストにも弱点はあります。
それは、市場の変化に弱いこと。
たとえば、Vue.jsだけに特化してきたけど、Reactが主流になってきた。
そうなったとき、再学習や転換のコストが大きくなってしまうことがあります。
AI時代の変化が、選択に影響を与えている
では、今の時代においてどちらが良いのでしょうか。
僕の答えはこうです。
自分の中にスペシャリストの核を持ちつつ、
ジェネラリストの幅で生き抜く。
特定分野での深い理解があることは、AIを使いこなす上で大きな武器になります。
なぜなら、AIは表層的な回答は得意でも、細かな実装や現場文脈までは読めないからです。
たとえば、AIにプロンプトを投げたとき、
本当に欲しいアウトプットを引き出すには、その領域に対する前提知識や文脈理解が必要です。
つまり、スペシャリスト的な視点を持っていないと、AIを使いこなすことができない。
一方で、AIによって業務の効率化が進んだことで、複数領域を横断できる“横幅のある人”へのニーズも増えています。
データ分析、UI設計、バックエンド、クラウド構成。
以前は分業されていた業務が、今では一人である程度回せることも珍しくありません。
だからこそ、設計が必要になる
つまり今は、どちらかに振り切るのではなく、
自分のキャリアにどうバランスを持たせるかを設計する力が問われています。
大切なのは、自分の中にこう言える軸を持つこと。
自分は、どの領域で価値を出す人間なのか
そして、どこまでなら横断的に対応できるのか
この言語化ができていると、面談でも評価でも、自分の立ち位置を正確に伝えることができます。
LEGAREAではどう考えているか
LEGAREAでは、「まずはスペシャリストの入り口を持つ」ことを重視しています。
たとえば、最初にテストエンジニアやフロント開発に特化する案件に参画し、ひとつの専門領域で土台を築いてもらう。
その上で、徐々にAPI開発や設計、要件定義へとステップアップしていく。
その過程で、現場だけでなくL-timesなどの社内開発に関わり、少しずつ横断的な視野を持ってもらう仕組みを作っています。
また、社内では自分の技術ポジションを定義する1on1やキャリア面談も定期的に実施しています。
スペシャリストでも、孤立しては意味がない。
ジェネラリストでも、深みがなければ薄く見える。
そのバランスを一緒に考える場を、これからも提供していきたいと思っています。
おわりに
自分は器用じゃないから、スペシャリストで生きるしかない
自分は浅く広くしかやれないから、ジェネラリストとして頑張るしかない
そう思ってしまう人も多いかもしれません。
でも大切なのは、どちらかを選ぶことではなく、
どんな形で自分の価値を作っていくかを設計することです。
そしてその設計には、仲間や上司、会社の方針が大きく影響します。
LEGAREAは、あなたがその設計を進める上で、土台となれる会社でありたい。
そう思っています。
次の一歩を、自分の意志で踏み出せるように。
その道の先に、専門性と自由が両立するキャリアがあると、信じています。